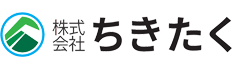再生可能エネルギーとは?
再生可能エネルギーとは、自然のサイクル、もしくは環境条件によって継続的に生み出されるエネルギーで
企業の経済活動を改善・継続していくためにも大変有意義な資源です。
太陽光・風力・水力・地中熱・地下水熱・温泉熱・地熱・太陽熱・バイオマス・温度差エネルギー(排熱)・雪氷熱などが
挙げられ、発電や、冷熱・温熱源として利用されています。
これらは省エネだけでなく、企業のコストダウンにも大変有効で、永続的な企業活動を支えます。
再生可能エネルギーの種類
近年、注目を浴びている再生可能エネルギー。
太陽光発電、風力発電、バイオマス、水力発電、地熱発電、太陽熱利用、雪氷熱利用、温度差熱利用、地中熱利用
大規模水力発電、地熱発電、空気熱発電などがあります。
海の水の温度差を利用した火曜温度差発電や、海の波力と潮汐など海流エネルギーを利用した
潮流発電等の研究も発展してきています。
風力発電
風車による風力発電は、風の力を利用したエネルギー発電です。
2000年以降から、日本への導入件数が増え、2016年度末で2,203基、累積設備容量は335.7万kWにものぼります。
風力発電の大きな特徴は陸上・洋上双方でエネルギーを生産することができること。
自然に発生する風を利用するため、昼夜問わず発電可能です。
風車の高さや羽のサイズによってエネルギーの容量は異なりますが、非常に効率的にエネルギーを生み出すことができます。
水力発電
河川の流水、農業用水、上下水道などの水を利用した発電。再生可能エネルギーの代表的な発電の一つです。
水資源が豊かな日本では大規模なダムだけでなく、近年、中小水力発電の建設も増えています。
水力発電の最大の特徴は安定した電力供給が可能である事と、発電所建設後は数十年と長期間に及び発電が実現できる事です。
二酸化炭素を排出しないことから、クリーンなエネルギーとしても周知されています。
太陽熱利用
太陽熱をエネルギー源とするため、エネルギー源確保のためには一切費用がかかりません。
省エネ対策として、企業だけでなく一般住宅用としても広く使用されています。
太陽集熱器に太陽熱を熱め、熱媒体と通して太陽熱をエネルギーとして利用するシステムです。
屋根に取り付けるなどして、太陽熱を取り組み、給湯や冷暖房に活用します。
エネルギー源は将来的にも無料ですが、設置費用、メンテナンス費用、ランニングコストはかかります。
太陽光発電
光が当たると、電気を発生するというシリコン半導体の特性を生かして開発された再生可能エネルギーです。
太陽の光を直接吸収し、直接電気に変換します。近来、日本でもっとも導入が増えている発電方法であり、
2016年度は累積で3,910万kWの電力を生み出しています。
エネルギー源である太陽光が無料であることや、特定の場所や地域などに捉われないため導入しやすく、
送電設備のない山岳部など遠隔地の電源や災害時の際の非常用電源としても、有効的に活用されています。
バイオマス
バイオマスとは生物資源(bio)の量(mass)を組み合わせた言葉で動植物等から生まれた生物由来の有機性資源のことです。
間伐材・可燃ゴミ、生ゴミ、廃油、下水汚泥、家畜糞尿等を燃焼または発酵(ガス化)し、タービンを回します。
タービンの回転によって発電機を動かし電力を生み出します。
廃棄物の再利用や減少につながるだけでなく、二酸化炭素を排出しないため、地球温暖化対策にもなります。
家畜排泄物、稲ワラ、林地残材、農産漁村のバイオマス資源を活用できますので、地球環境改善だけでなく、
農村漁村の活性化にも結びつきます。
地熱発電
地下の地熱エネルギーを使う発電方法です。日本は火山国のため、地熱利用した地熱発電所は1966年から
本格的に運転しています。電力量はあまりありませんが、東北や九州を中心に安定して発電を生み出しています。
発電に必要とされる高温の蒸気や熱水は、
農業用ハウス、魚の養殖、地域暖房等に再利用ができるという大きなメリットがあります。
1,000~3,000mに掘られた井戸の中で天然の蒸気を一日中噴出することがでる為、電力を休みなく産生する事ができます。
地熱エネルギーベースの為、石油、石炭、天然ガスといった化石燃料と違いエネルギー源が不足する心配もありません。
雪氷熱利用
雪や冬の冷たい外気を凍らせた氷を保管し、冷熱エネルギーとして利用するものです。
寒冷地のみと限られてしまいますが、自然エネルギーである雪を活用することにより、省エネや環境保全に貢献しています。
従来、莫大な費用を必要とした除排雪・融雪といった費用を抑えることにも直結しています。
米、酒、そば、野菜などを自然の冷気によって貯蓄する雪中貯蔵庫や、
雪氷冷熱エネルギーを利用した雪冷房マンションなど雪利用施設も増えつつあります。
地中熱利用
地表からだいたい近い200mの深さまでに存在する低温の熱エネルギーを地中熱といいます。
おおよそ地下10~15mくらいの深さの地中熱は一年中ほぼ同じ温度を保っています。
この安定した温度を利用し、季節や用途に合わせて冷暖房を行います。
外気温-15℃以下の環境でも稼働することができるため、設置可能な箇所をあまり特定しません。
ヒートアイランド現象の原因となる冷暖房熱を放出せず、放熱用室外機も必要ないため稼働時騒音も小さいのが特徴です。
しかし、初期費用がとても高いため、費用回収には長い年月を要することになります。
大規模水力発電
水の力を利用して発電する水力発電では、せき止めた川の水を高いところから一気に低いところに流します。
その流水の勢いで水車を回転させて電気をつくります。水の量、流れ落ちる高いに比例して、電力も増えます。
水力発電大きなメリットは、二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーであること、
エネルギー源が輸入する必要がなく純国産であること、自然界に存在する水がエネルギー源であることなどです。
地熱発電(フラッシュ方式)
エネルギー源を外国からの輸入に依存せずに、地球のマグマを利用した将来を期待される発電です。
生産井と呼ばれる井戸で、マグマから噴出するすざましい天然のエネルギーを蒸気として取り出します。
蒸気と一緒に噴出される熱水を分離し、蒸気のみを発電所に送ります。
蒸気の力でタービンを回転させ電気を生産します。熱水は還元井から地下深部へ戻します。
空気熱
ヒートポンプを利用し、空気熱による温熱供給あるいは冷熱供給を実現しています。
給湯器や空調用エアコン等に搭載されているのが一般的な使用方法です。
空気や他の物質を燃焼させることなく温熱供給、あるいは冷やすことなく冷熱供給するため、二酸化炭素を排出しません。
ヒートポンプにて、待機中から集めた空気熱を冷媒(CO2)に移し、圧縮機で圧縮します。
気体は圧縮されると熱くなるという性質があります。その性質を利用し、熱を水に伝えることで水を温めます。
次に、圧縮した熱を膨張弁で膨張させると空気熱を下げることができます。
冷媒(CO2)に集めた空気熱を圧縮あるいは膨張することで、熱をコントロールします。
再生可能エネルギーの特徴
二酸化炭素といった温室効果ガスの排出がない、あるいは微量であるという点が再生可能エネルギーの大きな特徴です。
水力・太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった自然エネルギー源を利用するため、
国内での供給が可能であることも大きな特徴の一つ。安全保障にも貢献した純国産エネルギーです。
日本国内において、徐々に再生可能エネルギーを電力に変換するシステムの導入は増加していますが、
2016年度現在、国内における生産実績は未だ全体の約15%程度に留まっています。
再生可能エネルギーのこれから
日本における再生可能エネルギー産生状況はかなり低い水準にあります。
2030年度までに、この数値22~24%へ伸ばし、再生可能エネルギーを国内主力電源とすることを目標としています。
再生可能エネルギーの主力電源化には、以下の課題に取り組む必要があります。
再生可能エネルギーの発電コストを低減
再生可能エネルギー導入後の企業等との意識合わせ
既存する電力系統を最大限に有効活用した再生可能エネルギー電源の確保
季節や天候に影響を受けても、停電などが発生しないための補助電力の確保
2014年度の電気事業連合会の発表によりますと、日本における水力を除く再生可能エネルギーは3.2%、水力は9.0%。
これに対して、非再生可能エネルギーの内訳は、天然ガス46%、石炭31%、石油10.6%となっています。
さらに非再生可能エネルギーにおける日本のエネルギー自給率は6%となり94%を海外からの輸入に頼っている状態です。
現代の私たちが生活する上で不可欠とされるエネルギー源の90%が、化石燃料である石油、ガソリン、天然ガスなどです。
これらは微生物の死骸や枯れた植物等が何億年という時間をかけ化石になり、石油や石炭になったと考えられています。
つまり、化石燃料は限りある物質であり、今のペースで使い続けると石油は約40年、石炭は約160年、
天然ガスは約70年でなくなってしまうといわれています。
残りわずかとなる資源を原料とする非再生可能エネルギーを、自然の恵みを活かした再生可能エネルギーに推移し、
主力電源とすることは、地球温暖化だけでなく、省エネ、エネルギーが枯渇した際の代替案といった観点からも、
もはや無視できない、必須事項といえるでしょう。